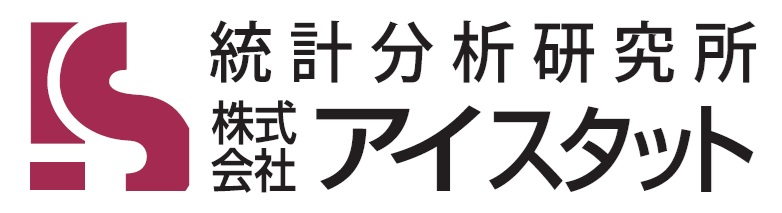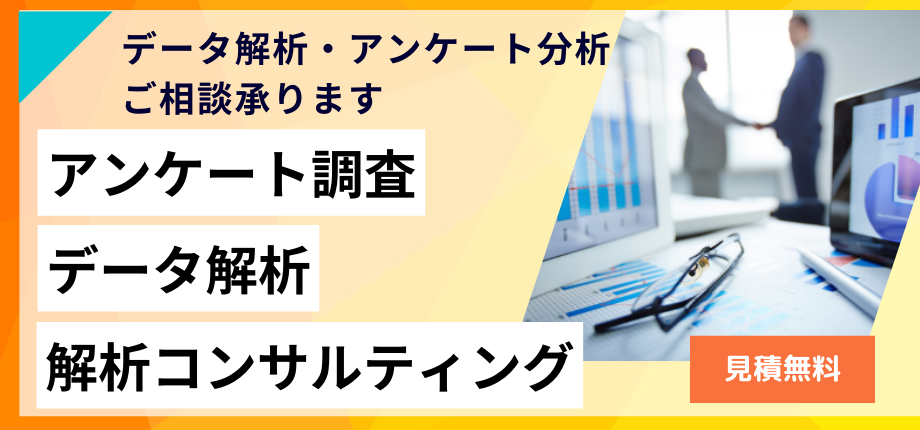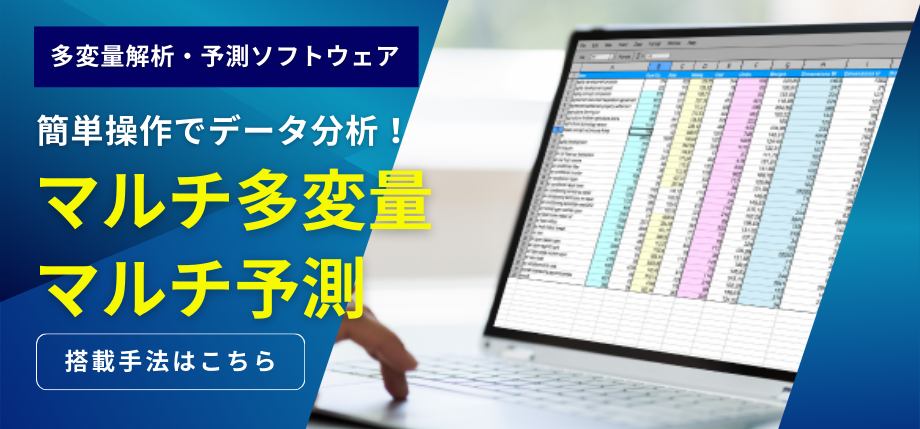母相関係数の無相関検定は、標本相関係数から、母集団の相関係数が0であるかを検証する検定方法である。
無相関検定は次の手順によって行う。
母相関係数の無相関検定の手順
①帰無仮説を立てる
母相関係数は0である。
②対立仮説を立てる
母相関係数は0でない。
③両側検定、片側検定を決める
両側検定、片側検定の概念がない。
④検定統計量を算出
検定統計量は相関係数の種類によって異なる。
⑤p値を算出
⑥有意差判定
p値<有意水準0.05(5%)
帰無仮説を棄却し対立仮説を採択する。
→母相関係数は0でない相関がある。
※高い(強い)相関があるということではない。
p値≧有意水準0.05(5%)
帰無仮説を棄却できず対立仮説を採択しない。
→母相関係数は0でないが言えない。
※「母相関係数は0(無相関)である」と言ってはいけない。
「有意な相関があるといえない」という言い方をする。
有意水準は通常5%を適用するが1%を用いることもある。
有意水準0.05と0.01から有意差判定を次のように行うこともある。
| p値<0.01 | [**] 有意水準1%で有意な相関がある |
| 0.01≦p値<0.05 | [* ] 有意水準5%で有意な相関がある |
| p値≧0.05 | [ ] 有意な相関があるといえない |